2020年より小学校ではプログラミング教育が必修化されましたね。
IT業界で働いていれば、その知識を我が子に教えてあげることもできますが、私のように特にIT知識がないママだと一体どうしたらいいのか…。
と、悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
親心としては、なんとなくでも構わないのでプログラミングというものを小学校入学までに理解しておいてほしいと思いますよね。
すでに入学されているお子様をお持ちの場合でも、なんとなくプログラミングがどういうものなのか子どもに知って欲しい…と思っているのではないでしょうか。
IT業界で働いている夫も、今後はどのような業界で働くことになっても英語の様ようにプログラミング知識・スキルはもっていれば就職時に断然有利になると考えています。
ただ幼児や小学生にプログラミングは早すぎる?と思う方も多いのではないでしょ。
確かにプログラムを組むというようなことになると、ITスキルがないと難しくなるかもしれません。
しかし幼児期の子どもにプログラムってどんなものなのかを伝えるのであれば、自宅でおもちゃや学習本を使って親子で一緒に楽しみながら学ぶことも可能だと思います。
実際に我が家は自宅近くのプログラミング教室に通わすことも検討しました。
しかしすでに長男は英語とピアノの習い事に通っており、これ以上習い事を増やすのは付き添う私がストレス…。
ということで、夫がプログラミングのおもちゃを使用して自宅でプログラミン学習を行っています。
今回は我が家で実際に使っているプログラミング学習グッズ3選をご紹介します!
プログラミングを遊びながら身につけたい!幼児期にぴったりな学習グッズ3選!
プログラミンググッズには色々なものがありますが、我が家では下記の要領で分けて3つを厳選しました。
- 学習本
- 遊びながらプログラミングの基礎が伝わるおもちゃ
- 初めはおもちゃのようだけれど、ゆくゆくはプログラムを組むことができるおもちゃ

我が家は夫がIT系知識があるので、夫にチョイスをお願いしました。

各おもちゃの特徴や人気・口コミなどから厳選しているので、子どももとても楽しそうにプログラミングを学んでくれています!
プログラミングを楽しみながら学べる学習本【学研のプログラミングがくしゅうちょう】
学研のプログラミングがくしゅうちょうというドリルを購入しました。
この学習帳の決め手は何と言ってもフルカラーなところ。
小さな子どもなので、カラフルな物の方が絵本のように興味がわきやすいようです。
実際に本屋で子どもに数冊のプログラミング学習帳を見せたのですが、これが良い!と言ったのでこれに決めました。
また内容もコンピュータはどこにあるか身近なものから探したりと、小さな子どもでも興味をもちやすい内容。
そして少しずつ論理的思考につながるフローチャート図などに取り組むようになっています。
フローチャートなど小さな子どもに難しそう!と感じるかもしれませんが、ゲーム感覚のような問題になっているので、とても楽しそうに子どもは取り組んでいます。
プログラミングを楽しみながら学べるおもちゃ【学研のプログラミングカー】
楽しみながらプログラミングを学べるもの…と探していたところ、たどり着いたのが学研のプログラミングカー。
学研のプログラミングカーは、口コミも良く「2018年のおもちゃ大賞」も受賞しており、おもちゃとしては間違いないおもちゃだと思います。
実際に4歳の長男と夫が週に3回程度、遊びながらプログラミング思考の感覚を養っています。
プログラミング思考と言われるとプログラマーになる人だけが必要な要素にも聞こえるかもしれませんが、一般的に企業で働く時にはこのプログラミング思考が必要とも言われています。

プログラミング的思考とは問題解決能力なので、どの企業でも必要とされるスキルです。
なのでうちの子はプログラマーになるわけではないから、プログラミング思考は必要ないと思っている方も多いかもしれませんが、問題解決能力を身に着けるという意味でプログラミングカーを使って感覚を養うことはとても良いことなのです。
長男は1週間程度でどんどんと使い方をマスターし、どんどんプログラミング思考を養っているように思います。
2歳の次男も興味津々♪さすがにまだ遊ぶには難しそうですが、お兄ちゃんと一緒に考える姿はとても可愛いです。
お値段も手ごろですし、これは3歳~小学校低学年のプレゼントにも最適だと思います。
アンパンマンやディズニータイプも登場して、ますますこのプログラミングカータイプのおもちゃは人気になっているようですね。
ゆくゆくはプログラムを組むことも可能なおもちゃ【Sphero mini Blue(スフィロ ミニ ブルー)】
最初は遊ぶおもちゃのようだけれど、もう少し大きくなったらプログラムを自分で組むことができるSphero社のスフィロミニブルー。
ピンポン玉程度の大きさのボールで、タブレットと連携して遊んだりプログラムを組んで動かしたりすることが出来ます。
長男はプログラミングカーである程度プログラムという存在を知ってから、こちらのスフィロミニブルーにも取り組むようになりました。
といっても、今はまだ遊ぶだけです。
でもこのスフィロ遊び方がとっても楽しい!
タブレットを傾けてボールを運転したり、指先でタップして動くのはもちろんですが、このスフィロミニブルーにはフェイスドライブ機能というものがあります。
顔の表情を認識して動いたり、止まったり、カーブしたりすることが出来るのです!
これが子ども達に大ウケ!
結構スピードも出るので、子ども達は追いかけたりもしてとても楽しく遊んでいます。
遊びながらも夫が長男に「もう少し大きくなったら、自分でプログラミング(命令)を組んでこのボールを動かすことが出来るよ」と声をかけると、とても嬉しそうにしていました。
今は遊ぶだけですが、もう少し大きくなった時に期待します。
2歳の次男でもタブレットを傾けたりするだけで動くのでとても楽しそう!
こうやって興味をもつだけでも、プログラミングに触れるきっかけには十分だと思います。
幼児へのプログラミング学習は自宅でも出来そう!
我が家のように両親どちらかがIT知識が少しでもあれば、自宅でのプログラミング学習は簡単に始められそうに思います。
夫も今の子ども達は楽しく学べるプログラミング教材が多くて羨ましいと言っています。
私は残念ながらIT知識が少しもないので、同じようにおもちゃを購入しても夫のようにプログラミング思考に繋がるように長男と会話をすることは時間がかかりそうに感じました。
おもちゃの操作については、ITスキルがなくても直感的に操作が分かるので問題ないと思います。
個人的にどの教材も親のフォローがあると、より本当のプログラミング思考が養われるように感じます。
両親にIT知識がなく教える自信がない場合、どうしても子どもに本気でプログラミングを学ばせたいと言う場合は、やはりプロにお願いした方がいいでしょう。
英語、音楽、スポーツ、IT。
知識がないものはプロに頼るに限ります!

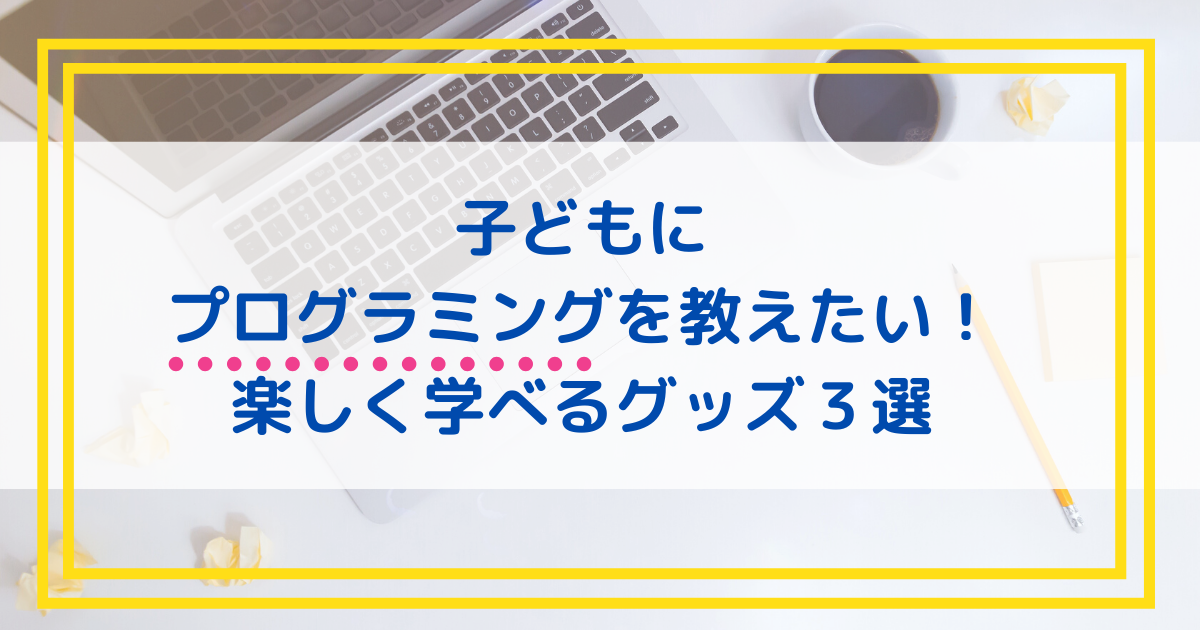



コメント